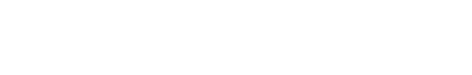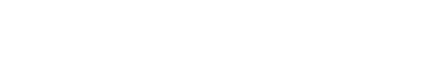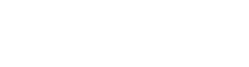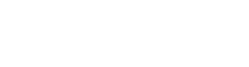芸術にマニュアルはない
創作過程


土づくり
300年以上昔の御庭焼高取の時代から伝わる白土。これを2〜3カ月かけて水で漉し、細かい粒子状の陶土に整えていき、その後数カ月寝かせます。


菊練り
土の硬さを均一にするとともに、空気抜きを行うための作業です。菊練りを丁寧に行うことで、ろくろはスムーズに回ります。


水引
土を薄く整える作業。鹿皮を縁に当てたり、「うちごて」と呼ばれる棒状の道具を器の内側に当て、手を外側に当てたりしながら形を整えていきます。


練りつけ
大型の作品を制作する際に使用する技法。ひも状にした粘土を巻いて積み上げ、おおよその形を作成したら、水を引いて一気に引き上げ、成形します。


ろくろ
味楽窯では「蹴ろくろ」を主に使用します。蹴ろくろとは木製のろくろで、自身で蹴って回転させるため、安定した回転を保つには技術が必要となります。蹴る速度を思い通りに調整しながら、手元で繊細な作業を行うには、非常に高度な技術と経験を要します。


乾燥
おおよそ成形した作品は、硬化させるために逆さにして1〜2日ほど乾燥させます。


削り
乾燥させた陶器の細かい部分を鉋(かんな)などで整える作業。口縁を傷つけないように湿台(しった)と呼ばれる円筒の上に、逆さにした陶器を乗せて作業します。


素焼き
乾燥させ、削った陶器を約800℃の窯で焼きます。


釉薬づくり
釉薬の原料は藁灰・木灰・長石・山錆(やまさび)などの天然素材。釉薬甕には、意図的に雨水をためて灰汁を抜いていきます。


釉薬がけ
釉薬は基本的に柄杓で陶器にかけ回し、そのまま余分な釉薬を落としていく方法をとります。二色に分かれた着色を行う場合は「掛け分け」という技法を使います。色の境目を筆で描き、それに合わせて柄杓で釉薬をかけ回すという手法です。


本焼き(窯入・窯出)
釉薬をかけた後に、一度乾燥させ、その後に約1280℃で本焼きを行います。